
発酵をあたらしくとらえ、
独自のスタイルで発信している、
注目のスポットやプロジェクトをご紹介。
日本のだし文化を世界へ。
フランスで発酵食品「本枯節」の生産を目指す
〈枕崎フランス鰹節〉の挑戦

実はかつお節が発酵食品であることをご存じだろうか? かつお節には大きく2種類あり、薪などを燃やし煙でいぶす「焙乾(ばいかん)」という工程を経た「荒節(あらぶし)」と、それにカビ付けして微生物による発酵を促し、旨み成分がさらに濃くなった発酵食品の「本枯節(ほんがれぶし)」がある。
“本物のかつお節”を世界に広めたいという熱い思いで〈枕崎フランス鰹節〉を起ち上げ、フランス・ブルターニュ地方の港町・コンカルノーにかつお節工場をつくった〈枕崎水産加工協同組合〉。薩摩藩といえば、かつてパリ万博に独自で乗り込んで力をアピールした歴史があり、失敗を恐れず新しいことを成し遂げていく頼もしいイメージがあるが、しかしなぜまたフランスでかつお節をつくることになったのだろうか。
「きっかけは2013年の視察旅行でした。枕崎のかつお節が『本場の本物』という食品産業センターの認定を受け、八丁味噌や碁石茶、山椒など日本の珍しい食材と一緒に選ばれて、フランス政府から食の祭典に招待されたのです。しかしかつお節は輸出ができなかった。伝統的製法によるかつお節は、EUの食品安全基準や衛生管理基準を満たしていなかったのです」
そう話すのは、〈枕崎フランス鰹節〉代表の大石克彦さんだ。
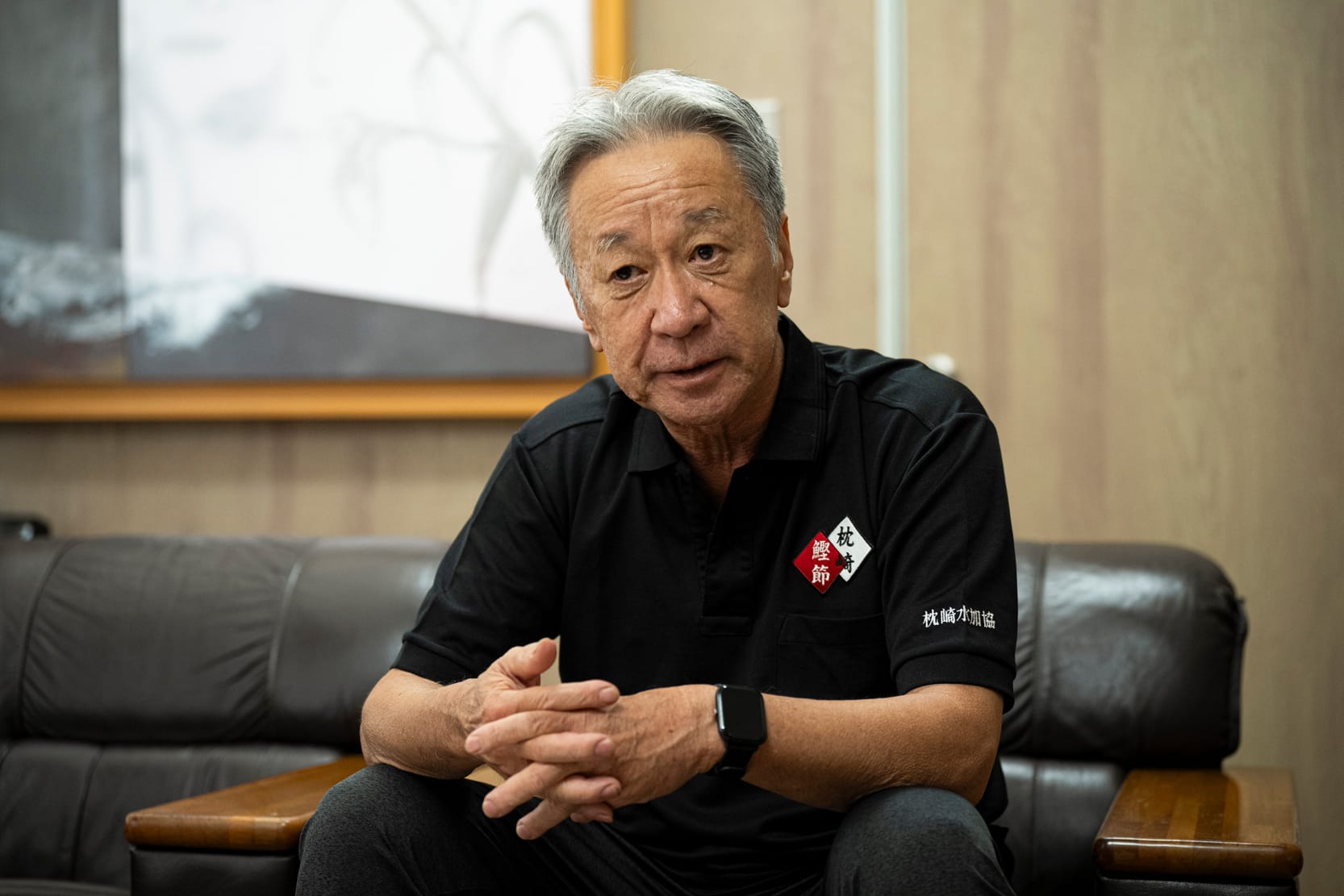
「鰹の水分を抜く焙乾の過程で煙から付着するベンゾピレンという物質が、発ガン性のリスクを伴うとのことで、EUでは輸入が規制されていました。日本の食品安全委員会では健康への懸念は低いと報告されていて、またベンゾピレンは水に溶けにくいため、だしにはほとんど含まれないのですが…」
行っても仕方がないとは思いつつ、ヨーロッパでのかつお節市場は未知だったので、せっかくだからと自分たちでかつお節を持参して渡航を試みた大石さん一団。思った以上に現地の評判は非常に良いものだったという。
「一流のシェフたちがとても興味を持ってくれたんです。一方でまちなかのスーパーなどを視察してみると、外国産の粗悪なかつお節が出回っていました。味も香りも良くなく、明らかにまがい物だと感じました。現地の人が運営する和食店と呼ばれる店では、かつお節の存在すら知られておらず、だしをとっていない味気ないみそ汁を出していました」
この現状にはがっかりしつつも、かつお節の価値をわかってもらえるポテンシャルを大いに感じていた大石さん。本物のおいしいかつお節をもっと広く深く知ってもらいたい、と強い思いが湧き上がった。
苦節4年…EUの基準をクリアする
かつお節ができるまで
「輸出に向けて政府に働きかけることも考えましたが、それでは何年かかるかわからない。では現地にかつお節工場をつくったらどうかと思い立ち、組合員たちに話してみたら、すごく盛り上がってしまって。まだフランスになんのツテもなかったのですが、試しに新聞社にこんな動きがあると話したところトップ一面で出してくれたんです。そこからテレビ局も黙っておらず、あれよあれよとNHK含む4社が取材に来てくれました。そうしたらすぐに東京のフランス大使館から連絡が来たんです。急いで次の日東京まで行ったら、全面的に協力してくれるという話でした!」
トントン拍子のように聞こえるが、その後実際に工場が建設され、会社が稼働するまでに3年以上の月日がかかり、とにかく苦労の連続だったと大石さんは言う。

「何度もフランスへ行き、朝から晩まで缶詰状態で打合せが続きました。問題が山積みで、辛くて精神的に参ってしまったこともありましたよ。そんななか大きな幸運だったのは、日本をよく理解する現地のフランス人スタッフが加わってくれたことです」
学生時代は日本に住み、日本語も堪能で、ロンドンで弁護士をしていたグエネル・ペリランさんが故郷であるブルターニュへ戻り、スタッフに採用された。支店長として立ち上げ前から関わり、日本とフランスの橋渡しに活躍してくれたという。

ただ、一番の問題はEUの食品安全基準と衛生管理基準である。フランスで製造するには、まずはかつお節の焙乾の過程で煙から付着するベンゾピレンの数値を、EUの基準値以下に下げなければならなかった。さらに伝統製法を重視する枕崎の従来の製法を見直し、国際的な衛生管理基準であるHACCP(ハサップ)による基準を満たさなければならない。

日本から乾燥前の鰹を何本も持ち込んでは、ベンゾピレンを基準値以下に落とす実験が繰り返された。焙乾はかつお節を芯から乾燥させ、風味豊かに仕上げるために重要な工程である。枕崎では薪を燃やしていぶすが、フランスでは専門の機械業者と一緒に試行錯誤し、質のいい燻製チップを活用して香りを移しながら、乾燥は熱源によって行う製法を独自に開発。品質は変えずに成分だけを落とす、自分たちが納得できる製法をようやく確立でき、同時に衛生管理基準も達成した。EUの基準を満たす「荒節」が完成したのである。

「始めた頃はできるかどうかまったくわかりませんでしたが、自分たちには長年培った技術がある。そこに自信を持ち、必ずできると信じるしかなかった」と力強い言葉で大石さんは言う。
鰹自体はフランスの大型漁船がインド洋・セイシェルで漁獲し、スエズ運河を経て工場近くの港に水揚げされる。脂分の少ない身の締まった、日本よりむしろいい素材が手に入るそうだ。

ヨーロッパの食卓に浸透しつつある
かつお節のこれから
「荒節」としてのかつお節ができたところでいざ販売活動である。現地で営む日系の問屋が全面協力してくれたことで、徐々に販路が広がっていった。
「もちろん、カビ付けして発酵させる『本枯節』の方がおいしいだしがとれます。ただ、その完成にはもう一段、超えるべき壁がある。まずは荒節で、きちんとだしをとる文化を広げていきたかったんです」
最初はフランスの日本食レストランから反応があった。パリでのラーメンブームの流れもあり、かつお出汁を使う現地のラーメン屋も増えてきた。やがてフランスの人間国宝といえる、国家最優秀職人章(M.O.F)を持つフランス人シェフ、エリック・トロション氏に高く評価され、彼がメディアで広めてくれたことにより、かつお節はフランス料理界にも広まっていった。
「フランスにはもともとフォン・ド・ヴォーなどのだし文化があります。エリックさんは『このやさしい味わいのかつお出汁をフランス料理と融合させればすばらしいものができる』と語ってくれました。今でも店で使ってくれています」

現地のスーパーマーケットでも販売され、一般家庭にも少しずつ浸透している。コロナ禍を経て、飲食店で使う業務用の売り上げが落ち込んだときも、全体での売り上げは落ちなかったそうだ。その理由は家庭用の小売が健闘したからだという。従来の外国産に比べたら値段は高いが、売上は初年度の2倍以上に伸び、その後も伸び続けているそうだ。無添加で健康的という視点でオーガニックスーパーなどからの引き合いも多いという。

さて、大石さんたちの次なる目標は、カビ付けして発酵させた「本枯節」を現地で生産することである。カビ付けはEUの規制上、これまた大きな難題であるが、薩摩の誇りともいえる伝統的な本枯節をいつかフランスで製造したいと願う大石さんたちは諦めることなくチャレンジを続けている。
「以前、現地で荒節をカビ付けの環境に置いて実験してみたら、同じようにカビが育ちました。フランスはチーズなど、カビ付けの歴史と文化を持っているので、私たちの技術と融合できますし、挑戦しがいがあると思っています」

「さらに、かつお節のだしを使った加工品、調味料などの開発にも積極的に取り組んでいるんです。本枯節の生産を実現し、かつお出汁の用途の幅を広げ、使いやすい商品を増やすことで、かつお節文化を世界に広めていきたいと考えています」
美食の国としてブランド力の高いフランスに工場をつくったことが結果的に強みになり、ヨーロッパはもちろん、世界からも注目され、〈枕崎フランス鰹節〉の世界への可能性はまだまだ広がっていきそうだ。



