砂糖不要でやさしい甘さが特徴。
「発酵あんこ」のつくり方

砂糖を使わずに、小豆と米麹でつくる「発酵あんこ」。発酵によってできるやさしい甘みが特徴で、ついつい食べ過ぎてしまいそうな味わいです。小豆の苦味やアクを取り除く「渋切り」作業をすることで、おいしく仕上がります。小豆の量で甘さの調整ができるので、慣れてきたら自分好みの甘さを見つけてみてはいかがでしょうか。

- 材料
- 小豆・・・200g
水・・・3カップ
自然塩・・・ひとつまみ
米麴(乾燥)・・・200g
ゆで汁・・・200ml - 準備物
- 鍋、ボウル、ザル、炊飯器、タオル、保存容器、温度計
\ つくり方 /
はじめに
手を清潔に洗う。保存容器を消毒しておく。小豆を洗っておく。乾燥麹をほぐしておく。
1
鍋に小豆と分量外の水をひたひたに入れ火にかける。沸騰したら強火のまま3分程度茹でてからザルにあげて水気を切る。


〈 ポイント 〉 小豆の苦味やアクを取り除く「渋切り」は、ひと手間ですが、やるとやらないでは大違い。仕上がりをおいしくするためにもぜひおすすめします。
2
鍋を一度洗い、小豆と水3カップを戻して火にかける。沸騰したら弱火に落としてコトコトと小豆がやわらかくなるまで茹でる。指で簡単につぶれるくらいまで茹でる。


〈 ポイント 〉 茹でている間に小豆がゆで汁から顔を出してしまった場合は、かたさにむらができてしまうので水を足してください。ただし、水を入れすぎると旨みが逃げ出してしまうので、あくまでもひたひたの水加減でコトコト茹でてください。
3
小豆をザルに上げて、60度になるまで冷ます。ゆで汁は後で使うので別に取っておく。

〈 ポイント 〉 60度以上で麴を混ぜると、麴が死んでしまい甘みが出ません。しっかりと60度まで下げましょう。
4
炊飯器に小豆、麴、ゆで汁200ml(足りない場合は水を足す。残ったゆで汁は残しておく)、塩を入れてよく混ぜ、保温ボタンを押す。フタを開けた状態でぬらしたタオルをかけ、8時間ゆっくりと火を入れていく。途中2~3時間ごとにやさしくかき混ぜる。タオルが乾いていたらぬらす。


〈 ポイント 〉 8時間経っても甘みが出ないときは、2~3時間保温を継続します。乾燥し過ぎていたら残ったゆで汁を少しずつ足します。入れすぎると水っぽくなるので注意してください。
5
できあがったら保存容器に入れて粗熱を取り除き、冷蔵庫または冷凍庫で保存する。

〈 ポイント 〉 日持ちは冷蔵で4~5日、冷凍は1か月を目安に使い切ることをおすすめします。
? どんな発酵 ?
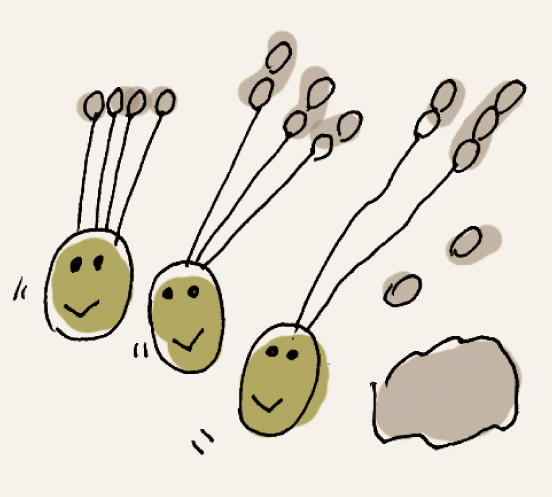
麹菌は蒸米(じょうまい)上で生育するとき、でんぷん分解酵素である「アミラーゼ」を生成し、米麹の中にため込みます。この米麹と小豆を発酵させることで、小豆に含まれるでんぷんがアミラーゼによって分解され、糖化します。そのため、砂糖を使用せずに甘いあんこができます。このとき糖化してできる糖は、「ブドウ糖(グルコース)」であり、砂糖(スクロース)よりマイルドなやさしい甘みとなります。
解説:金内誠(宮城大学 教授)/麹菌の詳細についてはこちら
\ たのしみ方 /
そのまま食べても自然な甘みがクセになる「発酵あんこ」。トーストやパンケーキにバターとともにトッピングしたり、もち米と合わせておはぎにしたり、お餅にのせたりとレパートリーは尽きません。冬の寒い日には少し水でといて温めれば、心も身体も温まるおしるこのできあがりです。


- 〈レシピ監修〉大島今日
- 1991年、宇都宮「オーベルジュ(現オトワレストラン)」にて料理の世界へ。24歳で渡伊。本場イタリアンレストランで3年間修行し、帰国後、東京丸の内「リストランテ・ヒロチェントロ」の料理長として就任。
その後、アル・ケッチァーノを経て、(株)フードアンドパートナーズへ。「Kouji & ko」のメニュー開発に携わる。発酵の旨みや香りを最大限に引き出し、おいしく、健康に配慮した料理を得意とする。




