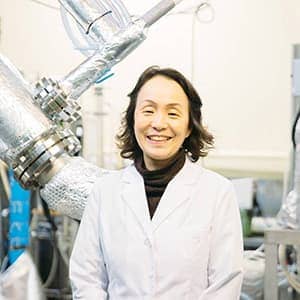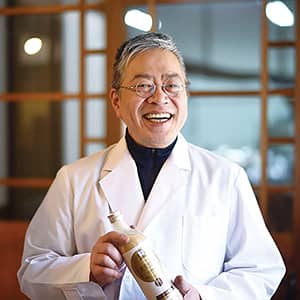発酵に関わる食文化や
商品開発、普及、研究を進める
発酵のプロにインタビュー。
〜わたしとカルピス®〜
発酵人たちが語るカルピス®の思い出

7月7日の七夕の日に誕生日を迎える「カルピス®」。日本初の乳酸菌飲料として1919年に誕生し、100年以上もの間、世代を超えて愛されてきた。「冷蔵庫の中にはいつもカルピス®があった」という子ども時代を過ごした人も少なくないだろう。
日々発酵に関わる“発酵人”たちは、カルピス®にどんな思い出があるのか。発酵デリカテッセン〈Kouji & ko(コウジアンドコー)〉料理長の大島今日(おおしまきょう)さんと、郷土料理家のminokamo(みのかも)こと長尾明子さんに、それぞれのカルピス®への思いを語ってもらった。
一杯で二度おいしい。
自分なりの飲み方を見出していた
岐阜県美濃加茂(みのかも)市で生まれ育ち、現在も、美濃加茂市近くの加茂郡七宗町神渕にある築100年の祖母の家と東京・世田谷区のスタジオとの2拠点生活を送るminokamoさん。郷土料理家として、地域に根差した食材の料理提案やイベントのプロデュース、フードスタイリングなど、多方面に活躍している。
そもそも“郷土料理”に関心を持ったきっかけは、社会人になって上京し、美濃加茂を離れたことだった。
「子どもの頃からよく食べていた岐阜県の郷土料理に“朴葉(ほおば)寿し”があります。酢飯に鮭や佃煮などを乗せて朴葉で包む、田植えの時期につくるものなのですが、東京にはどこにもない。『あれって岐阜にしかないんだ!』と初めて知り、郷土料理がいかに豊かなものかに気づかされました」

「祖母の家では、正月やお盆になると大勢の親戚が集まり長机を囲んでいました。賑やかで、みんなでお皿洗いをする時間でさえ楽しかった。郷土料理は、料理そのものだけではなく、料理を囲む空間を含めて味わうものなんだと祖母に教えてもらいました。そんな思いもあって、料理家としてメニューを考案するだけではなく、器選びやスタイリング、楽しい場づくりまで提供していきたいと活動しています」
発酵食との出合いも祖母の家だった。遊びに行くたびに「これを持って帰りなさい」と弁当箱やビニール袋に入った漬物を冬場は必ず渡されたという。
「ちょっと酸味のある白菜や赤かぶの漬物で、『もう一度食べたい!』と思っても市販品では通常なく、自分でつくるからこそ生まれる貴重な味だったんですよね。
子どもの頃は、近所のおばあちゃんが、長期間漬けて酸っぱくなった白菜の漬物の炒め物を『よかったらどうぞ』とよく出してくれました。戸惑いつつ口にしていましたが、食べてみるとすごくおいしい。大人になってから、あれが発酵食の味わいだったんだと知りました」

今では毎年木樽で味噌づくりをしているというminokamoさん。同じ木樽で白菜の漬物をつくるところが、自分なりの発酵食の楽しみ方なのだという。
「つくった味噌を食べきったあと、翌年の味噌づくりの前に木樽を空っぽにするんですが、染み込んだ味噌エキスを逃してはもったいない。そこに白菜と塩を詰めると、ほんのり味噌味が移った自家製漬物が完成します。発酵食は、常温で傷まないのもいいですよね。冷蔵庫に入れずに、自然の状態から離すことなく保存できるし、おいしくなってくれる。食べ物との良い接し方だなと思っています」

minokamoさんとカルピス®との記憶もまた、子ども時代に遡る。「当時、子どもが飲める甘くておいしい飲み物はカルピス®しかなかった」というほど、家にカルピス®がある風景は当たり前だった。
「当時のカルピス®は、紙で包まれた茶色い瓶に入っていて、我が家ではいつもシンクの下に置いてありました。ざらっとした手触りの紙をまくって、カルピス®と水と氷を入れていく時間がワクワクするんですよね。コップに入れたら、さっと混ぜて飲むのが、わたし流。最初にストローで下の濃くて甘いところを飲んで、最後に上のさっぱりしたところを飲むと後味もすっきりするんです。どうやったら一番おいしく飲めるのかと考えて、1杯で2つの味を楽しんでいたんでしょう。大事に飲んでいたんだなと思います」
冷蔵庫を開ければ、カルピス®と麦茶が並んでいる。「それが夏の風物詩と思えるほど、市民権を得ていたカルピス®はすごい」と当時を懐かしむ。

「氷を入れたときのカラカラとする音や、水玉模様を目にするだけでときめいてしまうのは、子どもの頃過ごした景色と結びついているからなのでしょう。ジュースや炭酸飲料水は飲ませてくれなかったけれど、カルピス®ならいいよと、安心して飲めるのもうれしかった。それもまた、乳酸菌飲料ならではの魅力かもしれません」
幼稚園で飲んだ“甘い飲み物”が、
カルピス®との最初の思い出
発酵デリカテッセン〈Kouji&ko(コウジアンドコー)〉の料理長を務める大島今日さんと、料理との出合いは小学生の頃。共働きで忙しかった母のために、コース料理を見よう見まねでつくったことが、“誰かに料理を提供する”初めての体験だった。
「テレビ番組を見てつくった、大した料理ではなかったはずなのに、『すごくおいしい! ありがとう!』と大喜びで食べてくれて。自分でつくったものでこんなに人が喜んでくれるんだ、という感激が、料理家を目指す原体験になっています」
大島さんが発酵食品に魅せられたきっかけは、新婚旅行で訪れた能登半島。へしこと出合い、その複雑な味わいに衝撃を受けたという。伝統的な発酵は文化であるという考えは、〈Kouji&ko〉のメニュー開発にもつながっている。
“発酵人”大島さんの記事はこちら→“おいしい” に思いを込めて。進化する発酵文化を伝える〈Kouji & ko〉|発酵ライフスタイル|発酵コラム|みんなの発酵BLEND
カルピス®との最初の思い出を聞くと、「一番古い記憶は幼稚園のときかな」と振り返る大島さん。金色の大きなヤカンに、普段は麦茶が入っていたが、「ときどき、白くて甘い飲み物をコップに1杯だけ入れてくれる」日があった。なんておいしいんだろう、もっと入れてくれないかなといつも思っていたと、当時を懐かしむ。

「金色のヤカンは魔法のランプみたいで、その甘い飲み物が出てくるときは心踊りましたね。小学生になってお中元で届いたカルピス®を飲んで、『あのヤカンの味はカルピス®だったんだ!』と記憶がつながりました。プレーンのカルピス®と、オレンジ味、グレープ味をきょうだい3人で奪い合うように飲んでいた。濃いめを飲みたかったので、自分がつくるときはいつもカルピス®多めでしたね」
大人になってから飲むことは少なくなったが、実は〈Kouji&ko〉の人気商品のなかには、カルピス®を使ったメニューがあるのだという。
「店舗で大人気の甘酒ヨーグルトドレッシングにはカルピス®が入っていますし、お子様向けのハンバーグのタルタルソースも、カルピス®が隠し味になっています。カルピス®はほとんどの人にとって”思い出の味“です。体がその味を記憶しているので、違和感なくスッと入って、『ほっとする味でおいしい』と懐かしさに体が喜ぶんです。万人に愛されるカルピス®だからこそ、記憶の扉をポンと開けてくれる力があるのだと思っています」

カルピス®の話を始めると、自然と顔がほころぶふたり。お互いのエピソードに「そうそう!」と共感し合う場面も多く、カルピス®が持つ“共通の思い出”の力を改めて実感したようだ。
後編では、カルピス®を使ったおすすめアレンジレシピを紹介してもらう。

- 発酵デリカテッセン〈Kouji&ko〉料理長
大島今日(おおしまきょう)さん - 丸の内の〈リストランテ・ヒロ チェントロ〉や、山形の〈アル・ケッチァーノ〉を経て、〈Kouji & ko〉のシェフに就任。発酵食品のイメージを変える、華やかな料理で話題を集めている。日本の発酵食品に興味を持ったのは、能登のへしこを食べたことがきっかけ。発酵学の第一人者、小泉武夫氏とも親交が深い。

- 郷土料理家・写真家・イラストレーター
minokamo(みのかも)さん - 本名・長尾明子。岐阜県美濃加茂市出身の料理家・写真家・イラストレーター。地のものを活かしたレシピ考案のほか、郷土食の紹介・執筆も手がける。東京・世田谷区と岐阜県にある築100年以上になる祖母の家を拠点にし、食に関するさまざまな活動を展開。著書に『つつむ料理』『粉100水50でつくる、すいとん』(技術評論社)、『みそ味じゃないみそレシピ』(池田書店)、『料理旅から、ただいま』 (風土社)などがある。