塩麹の次はコレ!?
麹を使った「発酵調味料」3選

蒸した米に麹菌を繁殖させた「米麹」は、日本の発酵食品をつくるのに欠かせないものです。味噌や醤油、みりん、米酢などの調味料をはじめ、甘酒や日本酒などをつくる際にも用いられます。かつては各家庭で味噌や醤油を仕込んでいたため米麹の存在は身近でしたが、今では味噌や醤油はお店で購入するのが当たり前の時代。米麹は脇役であり、発酵食品のつくり手以外にはあまりなじみのないものとなっています。
そんな米麹に注目が集まったのが2011年の塩麹ブームでした。大分県佐伯市にある老舗麹屋の女将が「再び麹が必要とされるように、味噌、醤油以外に麹を使った何かを開発できないか?」という思いで、江戸時代の文献をヒントに塩麹を生み出しました。そして、商標登録をせず、レシピも公開したことで大手メーカーなども次々と塩麹を売り出し、爆発的なブームに。その後、塩麹は調味料の一つとして定着しました。
現在もさまざまなメーカーが塩麹をつくっていますが、今回は麹を使ったレアな発酵調味料を厳選して3つご紹介します。
【その1. 〈カラカラ鬼糀〉】

〈カラカラ鬼糀〉は、唐辛子を使ったピリリと辛い麹調味料です。実はこれ、前述の塩麹ブームの仕掛け人である〈糀屋本店〉の浅利妙峰さんが手がけた渾身の作。大分県産の唐辛子と塩麹、青森県産ニンニクを絶妙な配合で混ぜ合わせたものです。いつもの料理にひとさじ加えるだけで、唐辛子やニンニク、麹の熟成した風味が加わり、おいしさがグンとアップします。
チャーハンや野菜炒め、肉炒めなどの調理中に加えるのはもちろん、冷やし中華やラーメン、味噌汁、パスタ、ピザ、鍋などに辛味調味料としてかけて使うのもOK。刺激的な辛味がありながら、辛いだけではない複雑な旨みも持ち合わせています。そして、和洋中エスニックのどんな料理とも相性がいいので、一度使うと手放せなくなりますよ!
▶︎〈カラカラ鬼糀〉について詳しくはこちら
【その2. 〈玄米甘糀〉】

〈玄米甘糀〉は、砂糖の代用品として使える発酵甘味調味料です。国産の玄米、米麹、伏流水のみでつくった甘酒をペースト状になるまで濃縮。一般的な甘麹は白米でつくることが多いですが、こちらの商品は栄養価の高い玄米を使用しています。いつもの煮物、焼き物、合え物の味つけとして使えば、玄米特有のコクと風味がプラスされ、ヘルシーかつ栄養たっぷりの滋味深い味わいに仕上がります。
〈玄米甘糀〉をつくるのは、発酵食文化が栄える石川県金沢市にある〈ヤマト醤油味噌〉。工場長の山本晋平さんは、糀甘酒の研究論文で博士号を取得した“日本初の甘酒博士”として知られる人物です。糀甘酒の深い知識と、職人としての卓越した製造技術を生かし、おいしさと栄養価にこだわり抜いた商品を生み出しています。
驚くほど濃厚で甘みたっぷりの〈玄米甘糀〉は、砂糖の代わりに調味料として使うのはもちろん、ジャムのようにそのままパンに塗ったり、かけたり、幅広くアレンジできます。
▶︎〈玄米甘糀〉について詳しくはこちら
【その3. 〈やさしいラー油〉】

〈やさしいラー油〉は、アメ色に炒めた玉ねぎと長ねぎ、ニンニクなど香味野菜を、有機栽培菜種油で炒め合わせ、長期熟成発酵した「玄米塩麹」のみで味付けした食べるラー油です。味の決め手である玄米塩麹は、1週間ほどで完成する塩麹が一般的ななか、半年以上寝かせたもの。旨みがグンと凝縮されていて味わい深くなっています。
つくり手は、千葉県香取郡にある〈発酵暮らし研究所&カフェうふふ〉の寺田聡美さんです。寺田さんは自然酒づくりで有名な酒蔵〈寺田本家〉の現当主(24代目)の妻で、23代目の次女。酒蔵に生まれながらも、実はお酒が飲めないという寺田さんは「私のようにお酒が飲めない人にも酒づくりの副産物を使った味を楽しんでほしい」と、酒粕や麹などを使った発酵レシピを考案しています。
〈やさしいラー油〉は薬味としてお豆腐にのせたり、麺類や鍋物のアクセントにそのまま使ったりするのがおすすめ。卵かけごはんに入れても抜群においしくなります。また、炒め物や和え物などの仕上げの調味料としてや、カレーの隠し味にも最適です。
▶︎〈やさしいラー油〉について詳しくはこちら
いつもの料理に使える、塩麹以外の麹調味料を3つご紹介しました。調理中に加えるのももちろん、食卓に置いてそのままちょい足しして使えるのもいいですね。毎日の食事にぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
-
-

-
発酵ライフを楽しむ〈発酵手帳2026〉文庫本サイズから拡張し、さらに手帳として使いやすく進化!
〈発酵手帳2026〉2025.12.12記事を読む
-
-
-

-
今年は歴史ある宿場町を舞台に開催!秋の行楽に出かけたい〈全国発酵食品サミットinとみや〉
〈全国発酵食品サミットinとみや〉2025.10.3記事を読む
-
-
-
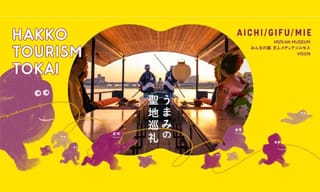
-
発酵で巡る!〈発酵ツーリズム東海〉で、2つの展覧会と50蔵、100のうまみ体験を楽しもう!
〈発酵ツーリズム東海〉2025.6.6記事を読む
-
-
-
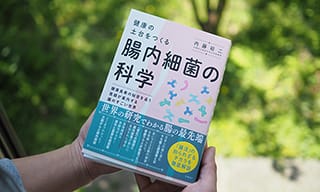
-
腸内細菌研究の第一人者、医師で教授の内藤裕二さんの著書が発売〈健康の土台をつくる 腸内細菌の科学〉
〈健康の土台をつくる 腸内細菌の科学〉2025.5.9記事を読む
-
-
-

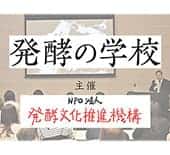
-
発酵界のスペシャリストに学ぶ!〈発酵の学校〉が第9期受講生の募集を開始
〈発酵の学校〉2025.4.25記事を読む
-
-
-
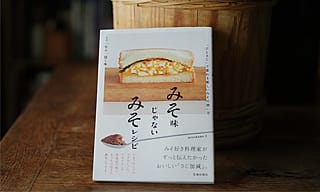
-
いつもの調味料を“みそめがね”で味噌に変換!味噌の色味で使い分けを提案する〈みそ味じゃないみそレシピ〉が好評発売中
〈みそ味じゃないみそレシピ〉2025.4.11記事を読む
-
-
-

-
乳成分不使用の「豆乳生まれのカルピス®」がリニューアルして再登場!
「豆乳生まれのカルピス®」2025.3.4記事を読む
-
-
-

-
砂糖不使用なのに甘い!チョコレートのような味わいの発酵カカオドリンク
〈HACCO CACAO〉2025.1.31記事を読む
-
-
-

-
「味噌」に「粕床」「発酵あんこ」も。自家製に勝るものはなし!? 冬に仕込みたい発酵食品3選
〈発酵レシピ〉2024.12.20記事を読む
-
-
-

-
発酵ライフを楽しむ〈発酵手帳2025〉365日、発酵食のある暮らしのすすめ
〈発酵手帳2025〉2024.12.13記事を読む
-
-
-

-
体がポカポカになるホットドリンク!家庭でつくれる「発酵しょうが×カルピス®」
〈発酵レシピ〉2024.12.6記事を読む
-
-
-

-
日本各地の発酵食品が今年も集結!千葉県香取市で開催の〈全国発酵食品サミット〉
〈全国発酵食品サミット〉2024.10.11記事を読む
-
-
-

-
冷蔵庫に常備決定!秋の食材をよりおいしくする、発酵調味料3選
〈発酵レシピ〉2024.9.27記事を読む
-
-
-

-
麹の風味とカルピス®の甘酸っぱさが絶妙にマッチ!「甘酒×カルピス®」のドリンクで栄養補給してみて
〈発酵レシピ〉2024.8.23記事を読む
-
-
-

-
「甘酒」に「麹入りゆず胡椒」「水キムチ」も!夏にピッタリな発酵食レシピ3選
〈発酵レシピ〉2024.8.5記事を読む
-
-
-

-
仕込んだ梅シロップの活用法。「梅麹シロップ×カルピス®」のドリンクはいかが?
〈発酵レシピ〉2024.6.14記事を読む
-
-
-

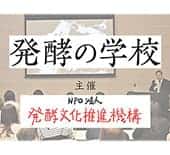
-
発酵界のスペシャリストに学ぶ!〈発酵の学校〉が第8期受講生の募集を開始
〈発酵の学校〉2024.5.10記事を読む
-
-
-

-
新年度に始めよう! 自宅で「発酵食品」づくり。春にぴったりのレシピ3選
〈発酵レシピ〉2024.3.29記事を読む
-
-
-

-
〈こうふはっこうマルシェ〉がパワーアップ! 2024年はワインツアーに発酵体験も
〈こうふはっこうマルシェ〉2024.2.22記事を読む
-
-
-

-
発酵でリトリート! 老舗・種麹屋が仕掛ける〈麹・発酵ホテル〉って?
〈麹・発酵ホテル〉2024.2.16記事を読む
-
-
-

-
発酵ライフを楽しむ〈発酵手帳2024〉2024年版は持ち運びに便利なスリム型に!
〈発酵手帳2024〉2023.12.15記事を読む
-
-
-

-
寒い冬には体の芯から温めよう。ぽかぽか「発酵レシピ」5選
〈発酵レシピ〉2023.12.8記事を読む
-
-
-

-
〈発酵カルピス®パーラー〉のクリスマス限定メニューは3種の爽やかな酸味とピスタチオクリームのコラボレーションが魅力
〈発酵カルピス®パーラー〉2023.11.24記事を読む
-
-
-

-
2023年の〈全国発酵食品サミット〉は岐阜県恵那市で開催!発酵がかもし出す、奥深くおいしい世界へ
〈全国発酵食品サミット〉2023.11.17記事を読む
-
-
-

-
発酵がおいしくした幻のバターがたっぷり。〈発酵 バターフィナンシェ〉が新発売!
〈発酵 バターフィナンシェ〉2023.10.6記事を読む
-
-
-

-
塩麹の次はコレ!? 麹を使った「発酵調味料」3選
〈発酵レア調味料〉2023.9.22記事を読む
-
-
-

-
夏バテにも、飲んだあとにも。からだがよろこぶ最強味噌「発酵ウコン味噌」って?
〈TABEL株式会社〉2023.8.18記事を読む
-
-
-

-
夏こそ食べたい!冷んやりおいしい「発酵レシピ」5選
〈発酵レシピ〉2023.8.4記事を読む
-
-
-

-
7月7日は「カルピス®の日」!〈発酵カルピス®パーラー〉に七夕シーズンメニューが登場
〈発酵カルピス®パーラー〉2023.6.9記事を読む
-
-
-

-
春〜初夏に楽しみたい「発酵レシピ」3選。季節の手しごとで発酵食品を仕込もう!
〈発酵レシピ〉2023.5.19記事を読む
-
-
-

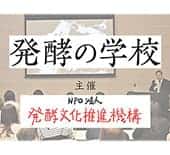
-
発酵界のスペシャリストに学ぶ!〈発酵の学校〉が第7期受講生の募集を開始
〈発酵の学校〉2023.5.12記事を読む
-
-
-

-
オープンから1年、〈発酵カルピス®パーラー〉の定番メニューがリニューアルして新登場!
〈発酵カルピス®パーラー〉2023.4.7記事を読む
-
-
-
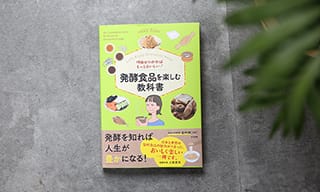
-
宮城大学教授、金内誠さん監修の新刊が発売〈理由がわかればもっとおいしい! 発酵食品を楽しむ教科書〉
〈ナツメ社〉2023.3.17記事を読む
-
-
-

-
小泉武夫博士監修の「発酵弁当」&スペシャルトークを満喫する〈発酵列車〉が運行!
〈発酵列車〉2023.3.2記事を読む
-
-
-

-
〈カルピス(株)発酵バター〉をぜいたくに使った〈発酵 バターサブレ〉が発売!
〈発酵 バターサブレ〉2023.3.1記事を読む
-
-
-

-
発酵&ジュエリー&クラフトに出会う! 〈こうふはっこうマルシェ〉が4年ぶりのリアル開催
〈こうふはっこうマルシェ〉2023.2.24記事を読む
-
-
-


-
世界初のチョコレート醤油「カカオ醤(ジャン)」が、ものづくり日本大賞・経済産業大臣賞を受賞
〈発酵エレメンツ〉2023.2.10記事を読む
-
-
-

-
すっきりorポカポカ。気分に合わせて選べる〈発酵カルピス®パーラー〉の冬限定メニュー
〈発酵カルピス®パーラー〉2022.12.16記事を読む
-
-
-
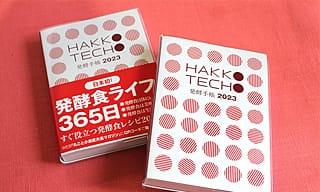
-
発酵ライフを楽しむ〈発酵手帳2023〉2023年版は旬の食材情報がさらに充実!
〈発酵手帳2023〉2022.11.25記事を読む
-
-
-

-
発酵食品を買って・食べて・学べる3日間! 秋田県横手市で〈全国発酵食品サミット〉が3年ぶりに開催
〈全国発酵食品サミットinよこて〉2022.10.7記事を読む
-
-
-

-
〈発酵カルピス®パーラー〉の秋限定メニューを味わおう
〈発酵カルピス®パーラー〉2022.9.30記事を読む
-
-
-

-
“発酵”をテーマにした観光連動型展覧会〈発酵ツーリズムにっぽん/ほくりく〉が北陸3県で開催!
〈発酵ツーリズムにっぽん/ほくりく〉2022.9.9記事を読む
-
-
-

-
世界初!? 大麦麹で発酵させた〈クロイツェル〉の〈発酵無添加ソーセージ&ベーコン〉が発売!
〈クロイツェル〉2022.9.2記事を読む
-
-
-


-
ひんやり発酵スイーツ「くず餅乳酸菌®️入りかき氷」で夏を乗り越える
〈船橋屋〉2022.7.29記事を読む
-
-
-

-
〈発酵カルピス®パーラー〉に夏限定メニューが登場!
〈発酵カルピス®パーラー〉2022.6.17記事を読む
-
-
-

-
発酵ソースを加えてフリフリ! 新感覚のオリジナルスイーツ〈カルピス®ゼリー〉って?
〈カルピス®ゼリー〉2022.5.27記事を読む
-
-
-

-
発酵食品×カルピス®の新しいおいしさを味わえる、ブランド初のコンセプトショップ〈発酵カルピス®パーラー〉オープン
〈発酵カルピス®パーラー〉2022.4.8記事を読む
-
-
-
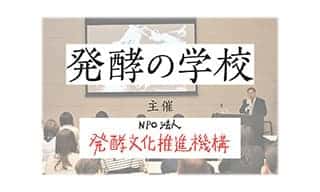
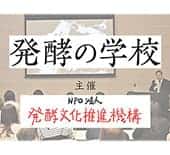
-
発酵界のスペシャリストに学ぶ!〈発酵の学校〉が第6期受講生の募集を開始
〈発酵の学校〉2021.4.1記事を読む
-
-
-

-
「持続可能な社会に大切なもの」に迫るフォトエッセイ。書籍〈子どもはミライだ!子どもが輝く発酵の世界〉
〈子どもはミライだ!子どもが輝く発酵の世界〉2022.02.25記事を読む
-
-
-

-
栽培から発酵、加工までこだわりぬいたチョコレートスイーツが勢ぞろい。大阪・名古屋で〈CHOCOLATE BANK〉がバレンタイン催事に初出展
〈CHOCOLATE BANK〉2022.01.28記事を読む
-
-
-

-
酒粕の個性を楽しめる、吟醸香漂う発酵スイーツ〈酒粕の吟(うた)〉が発売
〈SAKE Scene〉2021.11.26記事を読む
-
-
-

-
京都・河原町にて発酵イベント「ビルごと熟成 発酵体験」が開催!発酵の魅力を満喫できる特別な9日間!
〈GOOD NATURE STATION〉2021.10.29記事を読む
-
-
-


-
キーワードは“発酵”。陸前高田の発酵パーク〈CAMOCY〉で「カルピス」フェア開催!
「カルピス」フェア@陸前高田〈CAMOCY〉2021.6.28記事を読む
-
-
-
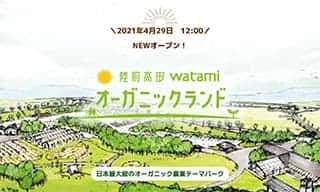
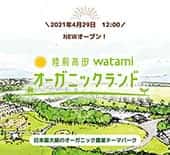
-
有機・循環型社会をテーマにした農業テーマパーク〈ワタミオーガニックランド〉が陸前高田に誕生!
〈ワタミオーガニックランド〉2021.4.30記事を読む
-
-
-


-
ナチュラルな発酵食を日常に。みりん粕や酒粕使用のエシカルスイーツ&スムージーブランド〈ORYZAE JOY〉に注目!
〈ORYZAE JOY〉2021.3.5記事を読む
-
-
-


-
「カルピス」とヨーグルトのダブル発酵!「発酵BLENDヨーグルト&『カルピス』」がリニューアル
〈カルピス〉2021.2.9記事を読む
-
-
-


-
発酵の面白さを堪能する!〈発酵デパートメント〉の「発酵精進ランチコース」
〈発酵デパートメント〉2020.12.11記事を読む
-
-
-


-
いま注目のバナナとの組み合わせ!「発酵BLENDバナナヨーグルト&『カルピス』」が登場!
〈カルピス〉2020.10.20記事を読む
-
-
-

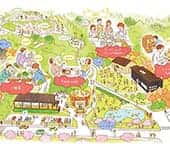
-
驚くような発酵体験ができる!発酵のテーマパーク〈OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~〉が埼玉に誕生
〈OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~〉2020.10.16記事を読む
-
-
-


-
「くず餅」は和菓子で唯一の発酵食品!?「くず餅×チーズ×味噌」のトリプル発酵スイーツ〈チーズくず餅プリン〉が限定販売中
〈船橋屋こよみ〉2020.9.11記事を読む
-
-
-


-
ヨーグルトとの相性抜群!いちご果汁を使った新しい「発酵BLEND」が2つのサイズで登場!
〈カルピス〉2020.8.25記事を読む
-
-
-


-
米どころ新潟の糀ドリンク専門店から、「玄米をもっと美味しく、もっと手軽に」がコンセプトの「玄米甘酒」をお届け
〈古町糀製造所〉2020.8.21記事を読む
-
-
-


-
西武池袋本店婦人服フロアにて初の発酵POP UP SHOP「発酵びびび〜美味しい・美しい・微生物が好き〜」オープン!
〈株式会社ルーシーケイ+日本発酵文化協会〉2020.8.11記事を読む
-
-
-


-
自然に、カラダに、農家にやさしい〈YASASHIKU Gelato(やさしくジェラート)〉が、老舗醤油メーカーから発売
〈YASASHIKU Gelato〉2020.7.15記事を読む
-
-
-


-
伝承の蔵付酢酸菌を配合。さわやかな酸味の〈酢酸菌入り くろ酢と炭酸〉で気分も爽快!
〈庄分酢〉2020.6.26記事を読む
-
-
-


-
料理家・脇雅世さんの『梅干し 漬け物 保存食』が新装復刊!おうち時間を活用して楽しもう
〈主婦の友社〉2020.5.22記事を読む
-
-
-


-
「カルピス」と「ヨーグルト」2つの発酵食品に旬のブルーベリーの組み合わせ!新しい「発酵BLEND」が登場!
〈カルピス〉2020.5.12記事を読む
-
-
-


-
日本全国、世界各地の発酵食品が大集合!〈発酵デパートメント〉のオンラインショップと実店舗が同時オープン
〈発酵デパートメント〉2020.4.28記事を読む
-
-
-


-
100年の歴史で初!豆乳を発酵してつくった新しい「カルピス」。「GREEN CALPIS」発売
〈カルピス〉2020.4.7記事を読む
-
-
-


-
生産者や職人が集結!〈木桶による発酵文化サミット in 東京〉でつくり手の情熱を感じる
木桶職人復活プロジェクト、D&DEPARTMENT PROJECT2020.3.19記事を読む
-
-
-


-
食べ比べもおすすめ。福岡〈UMEYA BRAINERY〉から、4種の酵母発酵チョコレートが登場!
〈UMEYA BRAINERY〉2020.2.25記事を読む
-
-
-


-
おいしくて不思議!〈全国発酵食品サミットinくまもと〉で、発酵の世界を知る
2/22(土)グランメッセ熊本2020.2.13記事を読む
-
-
-


-
発酵の魔法が土と食べ物、人を幸せにする。
映画〈いただきます ここは、発酵の楽園〉2020.1.31記事を読む
-
-
-


-
熊本県産サツマイモと生姜の〈ほんわか玄米あまざけ〉で腸活をスタート!
〈橋本醤油〉2020.1.31記事を読む
-
-
-


-
〈ホテルニューオータニ大阪〉で、熟鮓×フレンチ、中華。異色のコラボレーションが実現!
〈ホテルニューオータニ大阪〉2019.12.23記事を読む
-
-
-


-
〈oh dashi〉「発酵トマト×椎茸味」発売。液体だしをスープ感覚で味わう
スープ感覚のしいたけだし〈oh dashi(お!だし)〉2019.12.23記事を読む
-
-
-


-
テーマは抽出・発酵・蒸留!ノンアルコール専門店〈のん〉渋谷に期間限定オープン
〈the NON-AL STAND - のん -(ザ ノンアルスタンド ノン)〉2019.11.29記事を読む
-
-
-


-
新しい旅の出発点〈TABI BAR & CAFE from SUZUVEL〉が新潟を美食の街として輝かせる
〈TABI BAR & CAFE from SUZUVEL(タビバー アンド カフェ フロム スズベル)〉2019.11.29記事を読む
-
-
-


-
生活に取り入れやすい
発酵食品〈伝統発酵 くろず庵〉で
お気に入りの黒酢に出合う〈伝統発酵 くろず庵〉2019.10.30記事を読む
-
-
-


-
鮒寿し×チーズのマリアージュ。
〈Yoshio Fermented Foods〉が
琵琶湖の食を継承する〈Yoshio Fermented Foods〉2019.10.30記事を読む
-
-
-


-
〈「カルピス」みらいのミュージアム〉で、
「カルピス」の世界観を体感しよう〈「カルピス」みらいのミュージアム〉2019.9.25記事を読む
-
-
-


-
料理とペアリングも。
〈The D’or〉でワインのように
発酵茶を楽しむ〈The D’or〉2019.9.25記事を読む
-
-
-


-
甘ずっぱくさわやかなおいしさ♪
「発酵BLEND」りんご酢&カルピス発売〈カルピス〉2019.9.10記事を読む
-
-
-


-
リラックス効果がプラス。
八海山の「あまさけ」で、夏バテ防止〈八海醸造〉2019.8.28記事を読む
-
-
-


-
アレンジ自在!漬け物ブランド〈10%Iam〉が、発酵料理の可能性を広げる
〈10%Iam〉2019.8.28記事を読む
-
-
-


-
100%植物性なのにしっかり濃厚。「Hacco シェイク」で気分をリフレッシュ!
〈Hacco to go!〉2019.7.31記事を読む
-
-
-


-
この一冊があれば安心。『ぬか漬けの教科書』でぬか漬けを始める
〈ぬか漬けの教科書〉2019.7.31記事を読む
-
-
-


-
夏バテ解消!比叡山の星野リゾートで「お酢ベジ朝食」をいただく
〈星野リゾート テルド比叡〉2019.6.26記事を読む
-
-
-


-
子どもから大人まで楽しめる、発酵スポット〈魚沼醸造〉誕生!
〈魚沼醸造〉2019.5.29記事を読む
-
-
-


-
玄米麹の甘酒をつかった新潟生まれの「麹チーズケーキ」
〈キッチントラック「Mullet(マレット)」〉2019.4.24記事を読む
-
-
-


-
小倉ヒラクさんによる、発酵から再発見する日本の旅の展示が渋谷で開催!
Fermentation Tourism NIPPON〜発酵から再発見する日本の旅2019.4.24記事を読む
-




